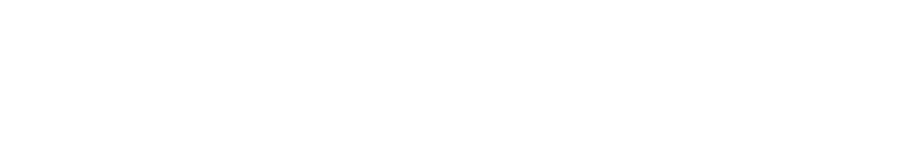中学受験に成功する子に共通する”お手伝いの習慣”
お子さんが机に向かう時間の大切さは誰もが理解していますが、実は「お手伝い」という日常のちょっとした時間が、子どもたちの可能性を大きく広げることをご存知でしょうか。
わが家では、中学2年の娘が毎朝のお味噌汁作りを担当しています。最初は具材を切るのも難しそうでしたが、今では「今日は小松菜を入れてみよう」と工夫を始めています。そんな娘の姿を見ていると、お手伝いは単なる家事の分担ではなく、子どもたちが自分で考え、挑戦する機会なのだと気づかされます。
お手伝いを通じて育つ3つの力:
家族の中学生は、朝の食器洗いを担当することで、学校に行く準備を逆算して考えられるようになりました。「あと10分で終わらせないと」という意識が自然と芽生え、テスト勉強の時間管理にも活きているようです。
近所の受験生のお子さんは、夕食後の掃除機がけが日課です。最初は面倒くさがっていましたが、「リビングはこう掃除した方が効率がいい」と自分なりのコツを見つけ出しました。工夫する習慣は、算数の文章題を解く時の発想力にもつながっているかもしれません。
また、食器の片付けや洗濯物たたみは、家族との何気ない会話の機会にもなります。受験のプレッシャーを感じる時期だからこそ、リラックスできるひとときが大切です。
こんな風に始めてみませんか:
「今日のお茶碗、ピカピカになったね」「ありがとう、助かったよ」。小さな成功体験と感謝の言葉が、子どもたちの自信につながります。でも、完璧を求めすぎないことも大切かもしれません。
時には失敗することもあるでしょう。でも、その経験が「次はこうしてみよう」という思考につながり、粘り強く考える力を育てていきます。
皆さんのご家庭でも、お子さんに合ったお手伝いの形があるはずです。「うちの子には何ができるかな」と、お子さんの興味や得意分野を観察してみてはいかがでしょうか。
答えは一つではありません。ただ、日々の小さな積み重ねが、お子さんの未来を支える大きな力になることは確かです。受験はゴールではなく、人生の豊かな学びの一つなのかもしれません。
2024/10/28 Category | blog