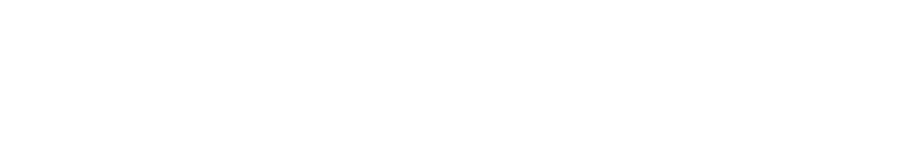中学生、定期テストの思考系の問題、どうしたらできるようになるの?
近年の定期テストで目立っているのが、暗記だけでは太刀打ちできない「思考力」を問う問題です。「なぜそうなるの?」「どうしてこの答えが導き出されるの?」と悩むお子さんの姿を、私は塾での指導の中でよく目にします。
実は、思考力を育むためには、日々の何気ない学習の中に芽があるのです。例えば、数学の関数の問題。単に公式を覚えるのではなく、「グラフがこう変化するのは、xの値がどう影響しているからかな?」と考える習慣をつけることで、徐々に思考力は育まれていきます。
最近の入試でも、千葉県や鳥取県の理科、高知県の数学では積極的に思考力を問う問題に取り組むなど、従来の知識偏重型の出題から、思考力重視の出題への変化が顕著になっています。この流れは定期テストにも確実に反映されているのです。
では、具体的にどう取り組めばいいのでしょうか?
私がいつも生徒に伝えているのは、「なぜ」を大切にすることです。例えば理科の実験問題。手順を暗記するのではなく、「この実験で何を確かめようとしているのか」「なぜこの順序で行うのか」を考えながら学習を進めることで、自然と思考力は養われていきます。
特に高校入試おいて、浜松北高など上位を目指す生徒にとって、この思考力を問う問題での得点が、大きな差となって表れることがあります。日々の学習の中で、単に答えを出すだけでなく、「どうしてそうなるの?」という問いを立てる習慣をつけることが、実は非常に重要なのです。
お子さんが問題に取り組むとき、すぐに答えを求めようとせず、一緒に考える時間を持ってみませんか?その積み重ねが、きっとお子さんの大きな力となっていくはずです。
2024/11/25 Category | blog
« 浜松西高中等部・静大附属浜松中:ディベート型の面接試験の練習は、家庭でもできますか? 本を読むことの大切さを子供にどう伝えたらいいですか? »