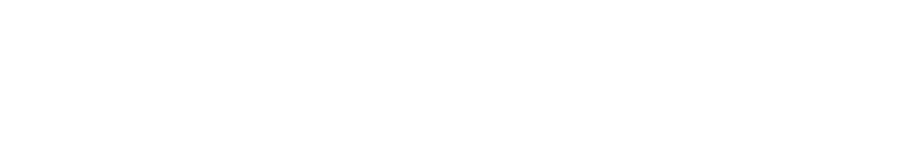【5/13付】意見を育てるニュース教室:思考の制御力を養う
新年度が始まり、GWが明けて3週間ぶりに「意見を育てるニュース教室」の授業を再開しました。今回は新たに1名の生徒を迎え、10名での授業となりました。
私たちのニュース教室では、「読む」「考える」「表現する」という活動を通して、子どもたちが自分の意見を育てていく力を養っています。今回は特に「思考の制御力」を意識した授業を小川先生が展開してくれました。
他の視点から考える力
授業の最初に取り組んだのは、生徒たちが関心を持ったニュースについての意見交換です。指名した2名の生徒は、それぞれ「宮内庁YouTubeの一部有料化」と「120年謎だったパズルの解明」について発表しました。
興味深かったのは、どちらの生徒も記事をそのまま受け入れるのではなく、自分の視点で問いを立てていたことです。一人は「税金でまかなわれている活動をなぜ有料に?」と疑問を投げかけ、もう一人は「正解が明確でない問題を懸賞として出題することの是非」を考察していました。
こうした「別の角度から見てみる」という思考の柔軟さは、いわゆる“水平思考”の一部です。
「水平思考の制御力」とは?
思考の幅を広げる力としてよく知られる「水平思考」ですが、ただ自由にアイデアを出すだけでは十分ではありません。「このアイデアは今使える?」「他の考えとどうつながる?」といった判断も同時に必要になります。
こうした自由な発想を上手にコントロールする力が「水平思考の制御力」です。
この力が育つと、以下のようなメリットがあります
- 発想のまとめ方が上手くなる
→ 自分の意見を筋道立てて話せるようになります。 - 難しい問題にも柔軟に取り組める
→ 一つの道がダメでも、「別の考え方」を試せる子になります。 - 他者の意見にも耳を傾けられる
→ 自分と違う考えにも価値を見いだせるようになります。 - 作文や発表に説得力が増す
→ 多角的に考えた内容は、読み手・聞き手に強く伝わります。
今回の授業では、まさにこの「水平思考の制御力」を育てる工夫が随所にちりばめられていました。
思考を深めるための“読む力”と“枠組みの理解”
続くニュースクイズでは、「体育の授業での水泳を始めたきっかけと、最近廃止となっている理由」について出題しました。この問題は図解も含まれており、情報を読み取りながら因果関係を考える必要があります。ある生徒が即座に正答したのは、日頃のニュースへのアンテナと読み解く力の積み重ねがあってこそでした。
「矛盾」という言葉についての問いでは、ある生徒が中国の故事までふまえて説明してくれました。言葉の深い理解は、深い思考を可能にする——そんな私たちの信念が、生徒たちの中に着実に根付いていると感じられる場面でした。
「具体と抽象」の理解から、思考の整理へ
最後に取り組んだのは、「具体→抽象」への関係性を問う問題です。たとえば「リンゴ→くだもの」のように、モノとそれが属するグループの関係を考える課題ですが、「線路と電車」や「花と水」など一見つながっているようでも、抽象関係ではないものも混ぜて出題しました。
この課題のねらいは、直感に頼らず、決まった“思考のルール”に沿って答える力を育てることです。これはまさに、思考をただ広げるだけでなく、整理し、絞り込む力にもつながります。
思考の広がりは、意見を育てる土台になる
「逆さまに考えてみる。一方向だけで考えていると、必ず行き詰まります」
小川先生の授業報告によれば、今回の授業では生徒たちがまさにその「逆さまから見る思考=水平思考」を実践していました。
そして、広がった思考をルールに沿って整理し、自分の言葉として表現する——その繰り返しが、子どもたちの「意見を育てる力」の土台になっています。
生徒数が増えてきたことで、今後はグループ討議なども取り入れ、生徒同士が直接意見を交わす機会も増やしていく予定です。異なる視点に出会うことが、思考をさらに深くし、自分自身の意見を豊かに育ててくれるはずです。
子どもたちが自らの言葉で「伝えたい」と思う姿を見ることほど、教育者としての喜びはありません。次回もまた、知的好奇心に火を灯す授業を届けてまいります。

どんなニュースに興味を持ち、どんなふうに意見を交わしているのか――
ぜひご覧いただけたら嬉しいです!
2025/05/15 Category | blog
« 文化祭・学校説明会シーズン到来! 浜松西高中等部・静岡大学附属中の中学受験を検討するご家庭が見るべきポイント 「国語を制する者が、受験を制する」浜松西高中等部や静岡大学附属浜松中に合格する勉強法をたっぷりと伝えます。 »