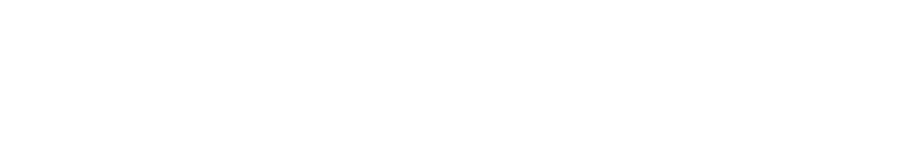他者の視点で書ける力、浜松北高合格に必須な文章スキル
保護者の方から嬉しいLINEをいただきました。修学旅行後の中3のお子さんの感想文を読まれて、「他者目線で書かれていることに驚きました」とのこと。多くの生徒が「もっと呼びかければよかった」「注意できなかった」と自分の行動を振り返るなか、そのお子さんはこう書いていたそうです。「クラスも学年も次にどう動けば良いかを考え、学んだことを活かして皆でさらに成長しよう」
自分の反省だけでなく、集団の未来に目を向けるこの視点。これこそが真のリーダーシップの芽だと感じました。保護者の方からの感謝の言葉をいただきましたが、実はこれは生徒自身の成長の証なのです。
文章における視点の広がりは、訓練で確実に伸びます。私が指導で大切にしている三つのポイントがあります。
一つ目は「主語チェンジ」。一度書いた文章の主語を「自分→仲間→先生→社会」と意識的に変えてみることです。視野が一気に広がります。
二つ目は「質問カード」の活用。「この出来事で誰が喜ぶ?」「別の立場ならどう感じる?」という問いを投げかけると、子どもの想像力は驚くほど拡がります。
三つ目は「家庭リフレクション」。お子さんの書いた文章を家族に読んでもらい、「良かった点」と「さらに深められる点」をそれぞれ一つずつ伝えてもらうのです。複眼的な評価が成長を促します。
哲学者アランは「嫌なことを我慢するのでなく進んで行う。これが心地よさの基礎である」と言いました。私は文章指導でもこの言葉を大切にしています。最初は視点を広げる練習が「面倒」と感じる子も多いものです。でも一度その心地よさを知ると、子どもたちは自ら多様な視点で考える喜びを発見します。
視点はレンズのようなもの。少しずつ揺さぶり続ければ、子どもたちは驚くほど早く「他者に届く言葉」を手にします。この力は受験だけでなく、将来を生き抜くための大切な翼になるのです。
今回の出来事を通して、改めて感じたのは、子どもたちの無限の可能性です。正しい導きがあれば、彼らは驚くほど豊かな視点を持ち、自分の世界を広げていきます。
浜松北高合格を目指す学習指導は、時に厳しさを伴うものですが、それだけにとどまらず、一人ひとりの心の成長も大切にしていきたいと考えています。知識を深めるだけでなく、自分以外の人や社会にも目を向け、思いやりと広い視野を持てる子どもたちへ――そんな成長を、温かく見守りながら支えていきたいと思います。
2025/05/10 Category | blog
« 『さぶ』を読む中学生たちの感想から見えてきたもの 文化祭・学校説明会シーズン到来! 浜松西高中等部・静岡大学附属中の中学受験を検討するご家庭が見るべきポイント »