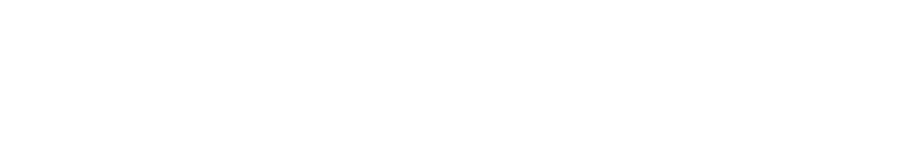【全国公立高校入試2025】数学入試の衝撃:もう「計算ができれば大丈夫」ではない時代
徳島県で出題された「計算なし」の数学問題
2025年度の高校入試で、数学の概念を根底から覆す問題が出ました。徳島県の入試問題です。
【徳島県 2025年度入試問題】
あるクラスの生徒30人にそれぞれ100点満点の国語と数学のテストを実施し、得点の分布を箱ひげ図で表した。この箱ひげ図から読み取れることとして、正しいといえるものを2つ選びなさい。ただし、得点は整数とする。
ア 国語と数学の平均点は同じである
イ 数学が5点以下の生徒は15人である
ウ 範囲も四分位範囲も、数学より国語の方が大きい
エ 8点以上をとった生徒の人数は、国語より数学の方が多い
この問題、一つも計算式が出てきません。でも、箱ひげ図からデータの性質を読み取り、論理的に判断する高度な思考力が求められています。しかも「データの個数や整数値という条件を使って論理的に判断する」ことまで要求されているのです。
島根県では「根拠を示して説明する数学」
島根県では、さらに衝撃的な問題が出ました。
【島根県 2025年度入試問題】
町役場では、よりよい交通サービスを提供するため、ある路線のバスの利用状況を調査した。平日20日間分の各時間帯におけるバス利用者数のデータを箱ひげ図に表した。
問: 上の図から、町役場の田中さんは、混雑することが多いと予想される11〜13時の時間帯にバスを増便する提案をした。田中さんの発言の①、②にあてはまる適切な言葉をそれぞれ答えなさい。
田中さんの発言: 「図から、11〜13時の時間帯をほかと比べると、中央値が ① こと、四分位範囲が ② ことがわかります。この2つのことから、11〜13時の時間帯にバスを増便することを提案します。」
もはや数学は「答えを出す」教科ではなく、「データから根拠を見つけて、政策提案の理由を説明する」教科になっているのです。
なぜ今、数学でも「説明力」なのか
理由は明確です。お子さんが社会に出る頃には、計算はAIがやってくれます。でも、「このデータは何を意味しているのか」「なぜこの結論が導かれるのか」を判断し、他人に説明する力は、人間にしかできません。
古代ギリシャの数学者ユークリッドは「証明なき主張は無価値である」と言いました。彼が重視したのは、答えそのものではなく、なぜその答えになるのかを論理的に説明することでした。2500年の時を経て、数学教育が原点に回帰しているのかもしれません。
空間図形でも「見えない平面を想像する」力
岩手県では、さらに驚くべき問題が出ています。
【岩手県 2025年度入試問題】
1辺の長さが4cmの立方体を2つ重ね、直方体にしたもので、点Pは線分AGと3点C、J、Lをふくむ平面との交点である。線分APの長さを求めなさい。

従来なら公式を覚えて代入すれば解けましたが、今は「この立体の中に、どんな平面を自分で想像すれば解きやすくなるか」を考える力が問われています。解説では「平面AIPCがその平面にあたります。空間図形を平面図形で考えることのよさを確認しておきましょう」とあります。
我が子は大丈夫?簡単チェック
お子さんに、こんな質問をしてみてください:
「クラスのテストの平均点が70点だったよ。君は80点だった。これについて、どんなことが言える?」
もしお子さんが「平均より10点高い」だけで終わったら、要注意です。新しい数学では「自分は上位何%くらいにいるのか」「この結果から何が推測できるか」「他のクラスと比べるとどうなのか」まで考える力が求められています。
長文問題で「数学的読解力」も試される
そして驚くべきは、数学でも複数ページにわたる長文問題が増えていることです。分析によると「数学的な思考力、考察力以前に、文章の読解力や長文に対する集中力が必要となってきています」とあります。
数学なのに、まず文章を正確に読み取り、何を求められているのかを理解する国語力が必要になっているのです。
時代は確実に変わった
いかがでしたか。これが、お子さんが受ける数学入試の現実です。
「数学は計算ができれば大丈夫」という時代は、完全に終わりました。データを読み取り、論理的に考え、分かりやすく説明する力こそが、新しい数学力なのです。
でも心配はいりません。毎日の会話の中で「なぜ?」「どうして?」を大切にするだけで、お子さんの数学力は確実に変わり始めます。計算ドリルより、親子の対話こそが、新時代の数学対策なのかもしれませんね。
2025/06/24 Category | blog
« 中学受験オンラインセミナーフォロー会6月【浜松西高中等部・静岡大学附属浜松中】 【6/24付】意見を育てるニュース教室:「書く」と「描く」の間で »