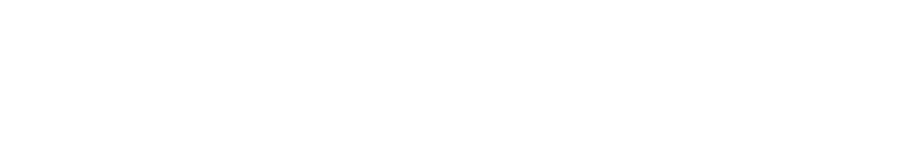【6/24付】意見を育てるニュース教室:「書く」と「描く」の間で
「絵は書くではなく、描くとするのが正しいから、『絵』が正解にはならないと考えたのです」
昨日の「意見を育てるニュース教室」で、6年生のAチームがこんな理由で解答を躊躇したと、小川先生から報告がありました。
作文パズルの問題で、空欄に「絵」を入れれば文脈的には完璧に通るのに、漢字の使い分けが正確でないからと、あえて「解答なし」を選んだのです。
この判断の深さに、私は驚きました。
多くの大人でも見過ごしてしまう「書く」と「描く」の違い。文字を「書く」、絵を「描く」。普段何気なく使い分けているけれど、改めて問われると曖昧になってしまう境界線を、この子たちはしっかりと意識していたのです。
哲学者ウィトゲンシュタインは「言語の限界がその人の世界の限界である」と言いました。正確な言葉を知ることは、正確な思考を身につけることに直結します。あの6年生たちは、無意識のうちにこの真理を体現していたのかもしれません。
でも、こんな疑問も湧いてきませんか。
「うちの子は、そんな細かいことまで気にしないかも…」 「もっと大雑把で、深く考えずに答えを出してしまうタイプなんです」
安心してください。言葉への敏感さは、一朝一夕に身につくものではありません。
大切なのは、お子さんが何かに疑問を感じたとき、それを「めんどくさい」「考えすぎ」と一蹴してしまわないこと。昨日のAチームの生徒たちも、最初は「絵でいいんじゃない?」という意見もあったそうです。でも、話し合いを重ねる中で、より正確な答えを求める姿勢が生まれていった。
この「もやもや感」を大切にしてあげることです。
「なんか変だな」「これで本当にいいのかな」そんな小さな違和感から、子どもたちの思考は深まっていきます。お子さんが宿題で立ち止まっているとき、友達との会話で首をひねっているとき。それは単なる迷いではなく、より正確な理解を求めている証拠なのかもしれません。
言葉に対するこだわりは、やがてものごとの本質を見抜く力に変わっていきます。表面的な正解ではなく、本当の意味での正しさを追求する姿勢。そんな子どもたちの成長を、私たちはどう受け止めればいいのでしょうか。
答えを急がず、一緒に考える時間を作ってみませんか。お子さんの「なんか変だな」という声に、ちょっとだけ耳を傾けてみてください。そこから始まる対話が、きっと思いがけない発見を運んでくれるはずです。

2025/06/25 Category | blog