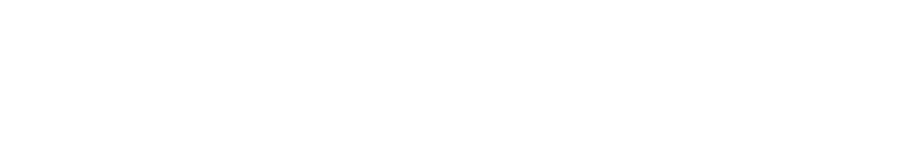学調と浜松北高
「なぜ頑張っても学調で結果が出ないのか」を根本から考える
浜松北高への切符を手にするために、9月の県学調(静岡県学力調査)で確実に結果を出したい。そんな気持ちを抱えているお子さんとご家庭は少なくないでしょう。
でも、なぜ多くの生徒が「頑張っているのに学調で思うような点数が取れない」のか。この根本的な問題に、今日は真正面から向き合ってみたいと思います。
「勉強している」と「結果が出る勉強をしている」の決定的な違い
25年間、浜松の子どもたちを見続けてきて、痛感することがあります。学調で210点を超える子と、180点台で伸び悩む子の差は、決して「勉強時間の長さ」ではないということです。
先日、ある中3生のお母さんから相談を受けました。「うちの子、毎日3時間は机に向かっているのに、模試の点数が上がらないんです」。
その子の問題集を見せてもらうと、答えを写すことに時間を費やし、「なぜその答えになるのか」を考える時間がほとんどありませんでした。まさに「作業」になってしまっていたんです。
学調で結果を出す子たちに共通しているのは、「自分の弱点と正面から向き合う習慣」を持っていることです。
弱点と向き合うための「敵を知り己を知る」学習法
古代中国の兵法家、孫子は「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」と言いました。これは受験勉強にも当てはまる普遍的な真理です。
「敵」とは県学調の出題傾向と問題レベル。「己」とは自分の現在の実力と弱点。この両方を正確に把握している生徒ほど、効率よく得点を伸ばしています。
例えば、数学で45点を目指すなら、計算・小問題(約30点分)は絶対に落とせません。でも「計算ミスが多い」と漠然と思っているだけでは改善しないんです。
実際に指導している生徒には、こんな分析をしてもらいます:
- 計算ミスは「符号」「約分」「移項」のどれで起きやすいか
- ミスをする時間帯や問題の種類はあるか
- 見直しの方法は適切か
すると「移項の時にうっかり符号を変え忘れる」「疲れてくる後半にミスが集中する」といった、その子特有のパターンが見えてきます。
この「個別診断」ができると、対策が具体的になります。移項の問題だけを集中的に練習し、後半で疲れないよう時間配分を調整する。こうして弱点をピンポイントで潰していくと、確実に得点が上がります。
夏休み後半戦:「選択と集中」の学習戦略
残り時間を考えると、すべての分野を完璧にするのは現実的ではありません。ここで大切なのが「選択と集中」です。
最優先で取り組むべき3つの領域
1. 確実に得点できる基礎問題の完全マスター
各科目で「これは絶対に落とせない」基本問題があります。数学なら計算・一次関数の基本・確率の基本問題。英語なら基本文法。社会や理科なら基本用語。これらで確実に120点分は確保できます。
2. 自分の得意分野での応用問題対策
理科が得意なら、計算問題(電流・化学変化・天体)に時間を投資する。社会が得意なら、グラフ・表の読み取り問題を集中的に練習する。得意分野で+20点を目指す方が、苦手分野で+10点を狙うより効率的です。
3. ミス防止の仕組み作り
どんなに実力があっても、ケアレスミスで20点失えば浜松北高は遠のきます。「見直しの手順」「時間配分」「マークミス防止法」など、本番で力を発揮するための準備が必要です。
具体的な弱点診断と対策の実例
数学でよくある弱点パターンと対策
パターン1:計算は合っているが、応用問題で式が立てられない → 問題文の「何を求めているか」を四角で囲む習慣をつける → 図やグラフから情報を整理する練習を毎日10分
パターン2:時間が足りずに最後の大問が白紙 → 各大問の目標時間を決めて練習(計算8分、関数12分など) → 分からない問題は2分考えて次へ進むルールを作る
英語でよくある弱点パターンと対策
パターン1:単語は覚えたが、長文が読めない → 毎日100語程度の短い文章で「主語・動詞」を見つける練習 → 接続詞(but, because, soなど)に印をつけて文の流れを把握
パターン2:文法問題で時間をかけすぎる → 文法は1問30秒以内で判断する練習 → 迷った問題は直感で答えて長文に時間を使う
9月2日当日に最高のパフォーマンスを発揮するために
県学調は一発勝負。どれだけ準備しても、当日の体調やメンタルで結果が左右されます。
最後の2週間は、知識の詰め込みよりも「本番力」を高めることに重点を置きましょう。
本番力を高める具体的な準備
- 毎朝8:30から50分×5科目の通し練習
- 問題用紙への書き込み方の統一(重要語句に○、計算スペースの確保など)
- 分からない問題での時間の使い方(2分ルール、後回し記号など)
- 休憩時間の過ごし方(次の科目の準備、軽い復習内容)
こうした「本番のルーティン」を身体に覚え込ませることで、当日の緊張や焦りを最小限に抑えられます。
保護者の方へ:お子さんを支える最適な関わり方
この時期、お子さんの勉強に対して「もっと頑張りなさい」と言いたくなる気持ち、よく分かります。でも、最も大切な親の役割は「安心できる環境を整えること」です。
- 勉強時間を監視するより、集中できる環境(照明、温度、静寂)を整える
- 点数の上下に一喜一憂せず、努力のプロセスを認める言葉をかける
- 「大丈夫、あなたなら必ずできる」という根拠のない信頼を伝え続ける
不安な気持ちを抱えるお子さんにとって、家庭が「ホッとできる場所」であることが、実は一番の学習環境整備なのです。
最後に:結果を出す生徒の共通点
経営学者のピーター・ドラッカーは「成果をあげる人とあげない人の差は才能ではない。習慣的な姿勢と基礎的な方法を身につけているかどうかの問題である」と述べました。
県学調も同じです。一夜漬けや根性論では太刀打ちできません。自分の現状を冷静に分析し、限られた時間で最大の効果を生む学習習慣を身につけた生徒が、9月2日に笑顔で帰宅することになるでしょう。
浜松北高という目標に向かって歩んでいるお子さんが、この夏の努力を確実に結果につなげられることを心から願っています。焦らず、でも着実に。一歩一歩、合格へと近づいていってください。
残り2名様限定 「9/2第1回学調対策:中3学調コンサルティング」では、お子さんの現在の学力と目標に合わせた個別の学習計画を一緒に作成します。この夏休みを、お子さんの人生を変える特別な60日間にしていけるよう、ぜひ一緒に歩んでいきましょう。お問い合わせはまなび研究所まで
2025/06/28 Category | blog
« 【6/24付】意見を育てるニュース教室:「書く」と「描く」の間で 小6中学受験・受験勉強に「空白の日」を作る意味 »