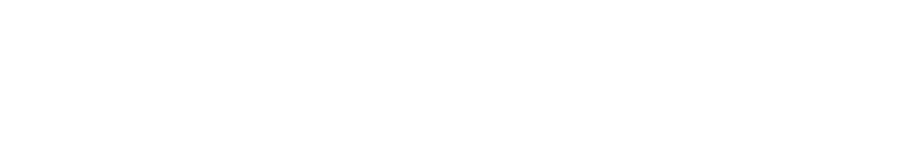【7/1付】意見を育てるニュース教室:つい口出ししてしまう親へ~子どもの『違う答え』が教えてくれた大切なこと
今週の小川先生の「意見を育てるニュース教室」で、とても印象深い出来事がありました。
作文のまちがいさがしの問題で、生徒たちに次のような課題を出したそうです。
【問題文】 「バスにはバス停があり、いつでもどこでも、乗れるわけではないので、不自由である。それに対して、タクシーにはバス停がなく、どこでも乗ったり降りたりできるので自由である。だから、バスよりもタクシーのほうが、自由に乗り降りできる乗り物だと言える。」
この文章の観点をそろえて、論理的に直すという課題です。
多くの生徒が「バスにはバス停があり、タクシーにはバス停がなく」という部分のおかしさには気づいても、どう直せばいいか悩んでいました。そこで先生が「バスもタクシーも何をするもの?」とヒントを出すと、「乗り物が出発したり、着いたりするところは?」という流れで「停留所」「発着場」といった抽象化した答えにたどり着いたそうです。
でも、一番驚いたのは、助言を受けなかったチームの答えでした。
「バスには時刻表があり、いつでも乗り降りできないので不自由である。それに対して、タクシーには時刻表がなく、いつでも乗り降りできるので自由である。だから、バスよりもタクシーのほうが、便利な乗り物だと言える」
出題者の意図とは全く違う答えでした。でも、この解答は論理的で、しかもとてもシンプル。「バス停」を「時刻表」に変えて、観点を「時間」という一点に絞って統一したんです。わずか6分という短時間で、この答えを導き出したのです。
小川先生は「よかれと思い、つい助言してしまうことが、逆に彼らの邪魔をしてしまう恐れがある」と振り返っています。
これを読んで、思い出したのは教育哲学者ルソーの言葉です。「子どもは自然に学ぶ。大人はただ、その邪魔をしないことが大切だ」。
私たち大人は、どうしても「正解」を知っているつもりになって、子どもに道筋を示そうとしてしまいます。でも、子どもの頭の中では、私たちが想像もしない創造的な思考が働いているんですね。
先日、お母さんからこんな相談を受けました。「うちの子は宿題をやっている時、私が見ていると手が止まってしまうんです。でも、一人でやらせると、変な解き方をしてしまって…」
その時、今回のニュース教室の話を思い出しました。もしかすると、その「変な解き方」こそが、お子さんの独創性の表れかもしれません。
大切なのは、子どもが考えている時間を「待つ」こと。答えが出るまで、じっと見守ること。たとえその答えが私たちの想定と違っていても、まずは「どうしてその答えになったの?」と聞いてみること。
子どもの思考プロセスを理解しようとする姿勢が、実は一番の教育なのかもしれません。
「つい口出ししてしまう」「答えを教えてあげたくなる」という親心はよく分かります。でも、時には一歩引いて、子どもの可能性を信じて待ってみる。そんな時間が、お子さんの創造性を育んでいくのだと思います。

2025/07/03 Category | blog
« 9月2日「第1回学調」で215点を突破するための、浜松北高合格を本気で目指す中3生のための個別コンサルティング 浜松西高中等部を目指す:大手塾では個別対応が不十分。息子の成長と合格に向けて筋道が見えない »